“しずまえ”こと、静岡県由比産の芭蕉梶木(バショウカジキ)
料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。
そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3747回目の今日も認(したた)めます。
今朝は、沼津魚市場で、

山口産の鱧(はも)と、

地物の目鯛(めだい)を仕入れました。
目鯛は、

昨日とは異なり、刺身用のものですので、目鯛としては、小さめのもので、昨日の目鯛については、こちらをお読み下さい。
同じなのは、

仕分けをしている最中に、

好みのものを選ったことで、“早起きは三文の得”とは、よく言ったものです。
先程お話ししたように、今日の目鯛は、

刺身に仕立てるため、脱水シートに挟み、冷蔵庫にしまおうとすると、ミニふぐ達がやって来て、

「親方、今日のブログのタイトルと目鯛の関係が分からないけど・・・。」
「でしょ♬」
「♬付のでしょって・・・。」
「まぁ、慌てなさんな。前置が長くなったけど、これからが話すからね。」
「はぁ~い。」
仕分けられた目鯛は、

このように売場に並んだのですが、

昨日、

この売場に並んでいたのは、

桜海老で有名な静岡県由比産の芭蕉梶木(バショウカジキ)で、最近では、

駿河湾に面している漁港で水揚げされている魚のことは、“しずまえ”と呼ばれています。
由比産の魚で、もっとも多く仕入れているのは、

さばふぐで、唐揚にして、お弁当の揚物に使っています。
また、芭蕉梶木は、さばふぐと同じ問屋が持って来たもので、その場に居合わせたので、「梶木なんて、由比の定置網にかかるんだぁ。」と訊くと、
「かかることは少ないんだけど、昨日かかったんだよね。この5本以外にも水揚げがあって、11本あったよ。」という答。
5本の芭蕉梶木の目方は、

33,0、

31,0、

23,0が、

2本あり、最後の1本は、
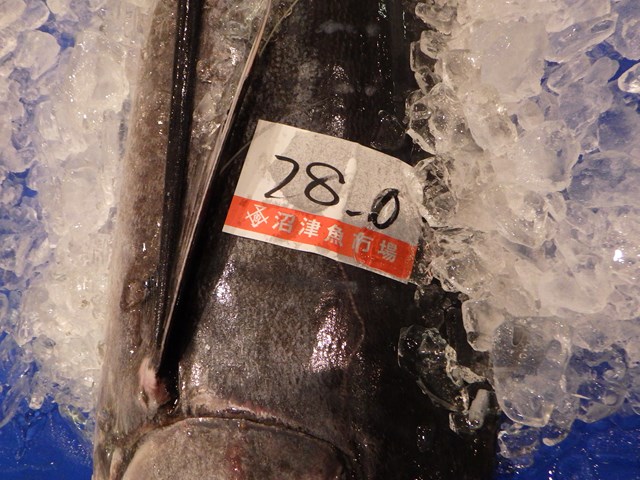
28,0で、言うまでもなく、単位はキロです。
見ているだけで、素通りしたのは言うまでもありません。
すると、ミニふぐ達が、
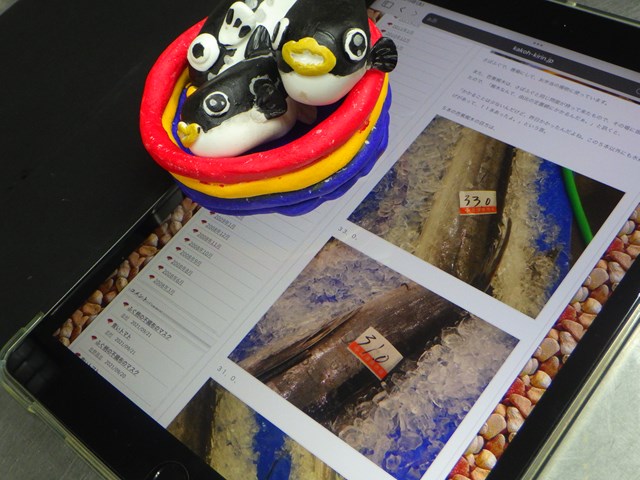
「親方、カジキマグロなんて言うけど、カジキはマグロなの?」
「違うよ。マグロはサバ科で、カジキには、マカジキ科とメカジキ科があるように、完全な別物。」
「じゃあ、何で、そんな風に呼ぶの?」
「 カジキが大型魚で、身質など、多くの点でマグロと似ていて、マグロの延縄で水揚げされるから、そう呼ばれるようになったよ。」
「 マグロの代用品ってこと?」
「そうなるんだけど、冬場の真梶木(マカジキ)は、別格の美味しさで、これまでに何度も使っているよ。」
「へぇ~。今日の芭蕉梶木は、どうなの?」
「食べたことはないけど、魚に詳しい魚屋に訊いたら、十分美味しいって。」
「ふ~ん。魚に詳しい魚屋って、変じゃね?」
「呼び方としてはね。でも、名前、違い、特性とか、色んなことを知っている人は少ないし、自分が使わない魚は、知らないもんだよ。」
「そんなもんなんだ~。あと、何で、親方は魚なのに、漢字で書くの?」
「カタカナで書くと、魚そのものになっちゃうし、漢字で書くと、料理になるからだよ。」
「・・・?」
「和食で献立を書く時は、魚の名前は、基本的に漢字だし、野菜も同じだよ。」
「だから、これまでも、そうだったんだ~。納得♬」
「あと、芭蕉梶木を仕入れることが出来たら、また教えてあげるね。」
「はぁ~い。」
芭蕉梶木に限らず、知らないというか、食べたことがない魚となると、一度が食べたくなり、もっと言うと、全ての食材についても、然りです。
この道に転がり、3分の1世紀が過ぎましたが、まだまだ知らないことも多く、「料理は、生涯勉強」を忘れることなく、仕事に臨み続けます。
















コメントを残す