一閑張りの河岸籠(かしかご)こと、市場籠(いちばかご)

その終わりで、

自分の河岸籠とか市場籠と呼ばれる2つの竹籠の手直しをしてもらうことを 、

お話ししました。
河岸籠というのは、魚河岸に買い出しに来る人達が買ったものを入れる籠で、市場籠とも呼ばれており、竹籠で今風に言うなら、エコバックということになり、竹を主にして作ったものですので、本当の意味で、エコバックとも言えます。
そして、昨日、

手直しを終えた河岸籠が届き、青と赤の二色なのは、自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さんをモチーフとし、青が自分で、

椿をあしらってあり、一方の赤の真由美さんの方には、

梅があしらってあります。
この二色は自分達の好みで、この方には、

天然のとらふぐをモチーフにしたマスクチェーン(マスクストラップ)を、作って頂きました。
ところで、折角の機会なので、このお揃いの一閑張りの作り方を教えてもらったので、お話しさせて頂きます。
持ち手を外し、 掃除したら、

下張りをし、張ってあるのは、和紙の原料の一つでもある楮(こうぞ)と呼ばれる植物の繊維が入っている和紙です。
十分に乾いたら、

内側にも紙を張るのですが、今回は、相撲の番付表をつかってあります。
この陽気ですので、乾くのは早く、十分に乾いたら、

外側に紙を張り、この工程を、外張りと呼んでいます。
先程同様、十分に乾いたら、

渋柿を塗り、乾いたら、

2回目を塗り、乾けば、出来上がりです。
ただ、 柿渋の茶色は、紫外線を浴びて、濃くなり、1年、2年と使い込んでいくと、色が変わってくるので、「 晴天の日には、お日さまに当ててあげて、末永くお付き合いください♬」とのことでした。
また、柿渋は、

このような商品で、

一応、渋柿ゆえ有害ではないものの、食用は不可のようです。
柿渋の2枚の写真を見ると、商品名もメーカー名も、“柿多冨(かきたふ)”で、ホームページも見てみると、色んな商品があったのですが、“柿多冨”なる名前に、趣を感じました。
日本料理の世界に身を置きながらも、日本文化について知らないことは多く、一閑張りもその一つでしたが、日本文化の一端を担う以上、色々なものを知るよう、努めたいものです。
★☆★ 日本料理の匠 ★☆★
【佳肴 季凛】店主兼熱血料理人の自分が、

このように紹介されております。ご興味、ご関心のある方は、上の写真をクリックして、ご覧下さい。
お取り寄せの『西京漬』や『鰯の丸煮』の発送の準備&側溝の掃除
ホームグランドである沼津魚市場は、土曜日の今日が休みですので、魚の仕込みをすることが少ないのですが、魚の仕込みがないからと言って、お気楽極楽とはいきません。
そういう時は、

仕込の労を厨房の掃除にあてており、女将兼愛妻(!?)の真由美さんと、洗い場の側溝の掃除をしたら、

明日発送する 『西京漬』 と、

『鰯の丸煮』の箱詰めをすることにしたのですが、

ギフト用ではなく、ご自宅へのお取り寄せということですので、

基本的に、一度使った食品の段ボールを使うことにしています。
レジ袋の有料化、SDGs (持続可能な開発目標)など、ごみの問題への理解もあり、殆どの方が、簡素な包装を了承して下さるのは、有難いことです。
ご注文の内容、個数も様々で、

『西京漬』と『鰯の丸煮』の両方もあれば、

『西京漬』のみ、

『鰯の丸煮』のみのものもあり、その都度、箱詰めして、

送り状を貼り、

養生をしたら、今度は、

厨房の側溝の掃除を始め、魚の仕込みがないながらも、せわしない一日が始まったのでした。
☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★
毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。
次回は、8月5日(木)の予定です。


放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。
一閑張りの竹箕(たけみ)

実用品の一閑張りということを書き、 その実用品が、

こちらで、営業中とあるように、

玄関に掲げておく看板というか、案内板です。
この案内板は、ざるではなく、竹箕(たけみ)で、竹箕という呼び方を知らなかった自分は、竹製のざるから検索し始め、ようやく辿り着き、日本人を50年以上やっていながらも、知らないものは、意外と多いのを、改めて感じました。
さらに言うと、日本料理という世界に身を置きながらも、日本的というか、和のものを知らないのは、少しばかり、気恥ずかしかったのですが、生涯、学ぶという姿勢を持ち続けなくてはならないとも、思った次第です。
この一閑張りの竹箕にも込められている意味があり、

営業中の文字が黒いのは、営業=商売が黒字になることを意味し、

金運にぶら下がるように、金の紐でかけるようになっており、“ふぐに魅せられし料理人”の自分ゆえ、

天然のとらふぐは欠かせず、自分のことを熟知している方ですので、ほぼ完璧です。
ところで、以前買い求めた河岸籠(かしかご)や市場籠と呼ばれる籠が2つあり、

一閑張りの魅力に取り憑かれつつある自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さんは、

リニューアルを依頼したのですが、この方のSNSを見ていたら、早くも作業を開始されたようで、完成品よりも、リニューアルの過程の方が楽しみでなりません。
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
一閑張りの盆ざる
『佳肴 季凛』のふぐギャラリーは、

“ふぐに魅せられし料理人”の自分にとっては、癒やしの場にして、萌え燃え・・・ 
真ん中に鎮座しているのが、

一閑(いっかん)張りの盆ざるで、一閑張りとは、 1620年代に中国大陸から渡来した飛来一閑(ひらいいっかん)なる人物が考案した伝統工芸品の紙漆細工です。
この一閑張りは、

例のポーセラーツのふぐの器を作って下さった方が、

新たなハンドクラフトとして始め、「以前からやってみたかったんですが、なかなか始める機会がなく、ようやくチャンスが出来たので、やることにしたんですよ~。試作だから、気に入らなければ、持って帰りますけど・・・。」と、遠慮しながら、持ってくれました。
見るやいなや、自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さんは、「凄い!熱烈歓迎!」と異口同音にして、頂くことにしたのですが、それまで、自分は一閑張りのいの字すら知らず、頂いたことにより、新しい知識を得ることも出来、嬉しい限りでなりません。
この盆ざるは、『佳肴 季凛』のために作って下さったものですので、

真ん中には2本の天然のとらふぐが描かれており、2本の意味するところは、

弘信とあるように、自分と真由美さんで、

書かれている文言は、

季凛の意味する“季を尊(たっと)び、凛とす”にはじまり、


『鰯の丸煮』などで、

当店の伝統工芸的なホームページさながらで、盆ざるをアレンジした工芸品というか道具とは言え、使うのはもったいないので、

癒やしの場のご神体として、飾ることにしたのです。
このご神体とは別の一閑張りの作品も頂き、そちらは実用品ですので、別の機会にお話しさせて頂きますが、最近では、この癒やしの場の写真を撮る方や、「SNSに投稿してあったふぐの器を見せて下さい!」と仰る方もいらっしゃり、知る人ぞ知るパワースポットになりつつあるような、ないような・・・。
☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★
毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。
次回は、8月5日(木)の予定です。


放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。
続・ふぐのイラストが描かれたポーセラーツの器色々
以前、『ふぐのイラストが描かれたポーセラーツの器色々』というお話しをしましたが、

その後、しばらくの間、女将兼愛妻(!?)の真由美さんと、萌え燃え・・・

或る日、自分用の湯呑みが、万事休す。
形ある物ゆえ、いつかは壊れるとは言え、半月程度ですので、 萌え燃え・・・
作って下さった方に、泣く泣く、この写真を送ると、「 あらあら・・・。形あるものですから、しょうがないです。 元気出してくださいな♬」と返信があり、

数日後、新しい湯呑みだけでなく、前回は無かった真由美さんの御飯茶碗も届けて下さり、真由美さん用ですので、胸びれのところには、2つの

そして、この2つでお仕舞いと思いきや、

別の日に、新しいシリーズがやって来て、MAXで萌え燃え・・・ 
その内訳は、

マグカップにはじまり、

5尾のふぐが描かれた丸皿で、 水色、ピンク、黄緑、黄、黒と、色違いの5色のふぐが描かれており、それぞれの向かい側にその色の
5尾5色と言えば、

先程の丸皿同様、ふぐをあしらった花びらの器で、花と言えば、桜であるのは、言わずもがなです。
“ふぐに魅せられし料理人”ゆえ、いつ何時でも使いたいのですが、やはり時季外れですので、使うというか、使いまくるのは、来春ですので、そのまま仕舞っておきました。
5尾5色に似ているのが、

3尾3色のふぐをあしらった角皿で、こちらは、水色、黄緑、ピンクと軽い感じの器です。
最後が、

醤油差(しょうしゅさし)で、ふぐゆえ、ぽん酢差というのが、正確かもしれません。
差(さす)の意味するところは、入れるで、平たく言えば、醤油入ということになるのですが、それでは、何とも味気なく、古来から日本人が重んじている風流、風情、粋のような趣は皆無です。
さらに、醤油差という呼び方をされる方がどれほど、いるのかと気になってしまいました。
この醤油差をお客様にお出しするのは憚られますが、常連さんや今回のお話しをお読みになった方には、

この角皿を、ふぐ刺用にお出ししてみようかと思っていますので、お気軽に声を掛けて下さい。
ふぐグッズについては、これら以外にも色々とあるので、機会を見て、お話しさせて頂きますので、乞うご期待!
★☆★【佳肴 季凛】のFacebookページ 更新中 ☆★☆

様々なお知らせを御覧頂くことが可能ですので、お時間が許すようでしたら、お立ち寄り下さい。「いいね!」、フォロー大歓迎ですので、宜しくお願いします。
青いラップ
料理をする際、もっとも使われていると思しき消耗品と言えば、

ラップで、一般的には、

無色透明です。
ラップという言葉は、サランラップを省略したように思われている方も多いようですが、サランラップは商品名にして固有名詞で、こういう類のものは、意外と多く、ホッチキス(ホチキス)も、その一例で、色々とあるようなので、調べてみて下さい。
ところで、先日、包装資材店から、

サンプルとして、

青いラップをもらいました。
中を開けると、

文字通りの青で、

使い勝手も全く同じです。
そもそも、何故ラップが青いかというと、 一般的な食材の色で、青は無いからなので、ラップの切れ端が料理や食材に混入した場合、見つけやすくするためで、青い色の料理や食材と言えば、かき氷のブルーハワイくらいかもしれません。
ところで、料理の世界で、青と言えば、野菜の緑を指してのことでもあり、それらを青味(あおみ)とも呼んでいます。
また、青魚の皮目の一部がそうなるかもしれませんが、色彩的には青とは呼びがたいような気がしますし、いずれにせよ、青は自然界にはあんまり存在しないのが、実情です。
青いラップは、我々のように対面で料理を提供する場合よりも、 食品工場、介護施設、給食調理を行う場などで使用されるケースが多く、存在は知っていても、手に取るのは、今回が初めてでした。
食の安全という点から、青いラップというのは望ましいのですが、青いラップに限らず、プラスチック製品は、SDGs(持続可能な開発目標)の観点をはじめ、脱炭素の問題にして、ごみの問題にも関わるので、一筋縄ではいかない面もあり、色んな立場の人達が、一度立ち止まってみる時なのかもしれません。
★☆★【佳肴 季凛】のFacebookページ 更新中☆★☆

様々なお知らせを御覧頂くことが可能ですので、お時間が許すようでしたら、お立ち寄り下さい。「いいね!」、フォロー大歓迎ですので、宜しくお願いします。
『西京漬』や『鰯の丸煮』用のセール品の化粧箱
今朝、

沼津魚市場で仕入れたのは、

『西京漬』用の5,3キロのサーモン(ノルウェー産)だけでした。
とは言え、 御中元用の『鰯の丸煮』に仕込むため、

生の真鰯の入荷があれば、仕入れるつもりでしたが、全くもって入荷がなかったので、サーモンだけになった次第です。
さらにいうと、6月30日の今日は、いわゆる締め日ですので、必要以上の仕入れを避けたかったこともあり、そういう点では、好都合でもありました。
その好都合を後押ししたのは、東京・豊洲をはじめとする中央市場の休みが今日だったことで、

送りと呼ばれる全国各地か送られてくる魚も少なく、さらに、

このところの悪天候も影響し、地物の水揚げも多くもなく、後ろ髪を引かれることなく、仕入れを終えたのです。
その後、向かったのが、

魚市場近隣にある折屋で、折屋とは包装資材店で、袋、ラップなどの消耗品にはじまり、器や道具なども扱っており、折屋という呼び方は、飲食業界でのそれで、中に入ると、

化粧箱、お弁当の折が無造作に積まれ、

“SALE!!”と書かれており、物色すると、

『西京漬』や『鰯の丸煮』に使っている化粧箱と、遜色なく使えるものを選り、化粧箱の殆どを超破格値で購入することにし、 輪をかけて“SALE!!” となり、嬉々としながら、魚市場を後にしたのでした。
『佳肴 季凛』に戻り、出汁を引くなどのルーチンの段取りを済ましたら、

サーモンの下処理に取り掛かり、鱗が細かいサーモンは、すき引きという包丁を使う方法で、鱗を取り除きます。
そうこうしていると、女将兼愛妻(!?)の真由美さんがやって来て、

化粧箱を指差した自分が、「これ全部でいくらだった思う?」と訊くと、「その言い方だと、かなり安かったんだよね~。」との返答。
20年以上連れ添いというより、連れ添ってくれ、必要以上の仕入れとも言うべき爆買いをする性分を分かっているので、「○※▲☆円!」と伝えると、「え゛っ!?お中元の時季だけに、ちょうど良かったじゃん。」と言い、仕事を始めてくれ、

箱詰して冷凍しておいた『鰯の丸煮』と、

『西京漬』の包装をし、

その頃までに、

頭を落とし、水洗いをしたら、

3枚に卸し、

切身にしたら、

有機JAS認証済の西京味噌をベースにしたお手製の西京味噌と共に、袋に詰め、サーモンの仕込みが終わりました。
丸つまり1本のままの魚を、鱗取りの下拵えをした場合、

まな板周り、

コールドテーブルと呼ばれる冷蔵庫、

床や側溝の掃除が不可欠で、魚を仕込まない日が続いても、側溝の汚れを確認し、場合によっては、掃除をしなくてはなりません。
そして、ランチの営業時間が終わると、

明日以降の仕込みに備えて、西京味噌を合わせたり、

真空パック用の袋を準備していると、

『西京漬』や『鰯の丸煮』を発送し、しばらくの間、今日のような日が続くことになります。
☆★☆ 通販サイト『そのまんま通販』 ★☆★
当店のお取り寄せや通販の商品は、直接の御注文だけでなく、
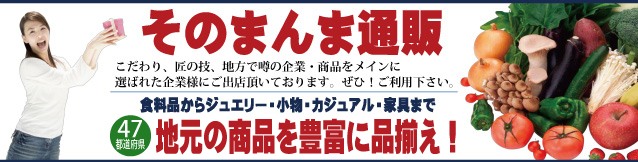
【そのまんま通販】の当店のページからのご注文も可能です。是非、ご利用下さい。
フードプロセッサーの新しい刃

その時に使ったのが、

フードプロセッサーで、

料理業界で多く使われている、いわゆる業務用のフードプロセッサーのメーカーは、

クイジナートというアメリカの会社です。
また、業界ではクイジと呼んでいるだけでなく、今や英語圏では、クイジナートはフードプロセッサーの代名詞になっており、クイジナート(Cuisinart)は、料理を意味するcuisine(クイジーン)と芸術を意味するart(アート)の混成語でもあります。
業務用であれ、家庭用であれ、フードプロセッサーの構造は大体同じですが、

先週末、使い終わったら、

刃の部分に亀裂が入っていることが分かり、

このような状態で使う訳はいかず、最悪の場合、片刃の状態で使うことも考えていたのですが、

分かった時点で、ネットで注文し、

ちょうどタイミング良く、

梅の仕込みをしている最中に届き、

早速使うことにし、“先輩”の刃は、

片刃としての日の目を見ることなく、お役御免となり、長年の労をねぎらい、お清めの塩をしました。
本体を購入してから、15年以上経っているのですが、毎日使う道具でもなく、使い方も激しくないので、モーターは何ら問題なさそうで、しばらくは使えそうです。
また、業務用の道具は、部品だけを購入することが可能であるだけでなく、本体そのものが廃番(製造中止)になっても、部品だけが対応出来ることもあり、今回のケースも然りでした。
昨今、SDGs(持続可能な開発目標)なることが叫ばれていますが、いたずらに新製品を開発し、販売するだけでなく、工夫次第では、必要最低限のアレンジで済むはずです。
かの疫病により、様々な変化、変革が求められつつありますが、国や地方の先頭に立つ方達こそ、新しい取り組みをし、一般市井の人々の範となるような姿を見せて欲しい限りでなりません。
★☆★ 日本料理の匠 ★☆★
【佳肴 季凛】店主兼熱血料理人の自分が、

このように紹介されております。ご興味、ご関心のある方は、上の写真をクリックして、ご覧下さい。
直しを終えた砥石
今日は定休日ということもあり、女将兼愛妻(!?)の真由美さんと沼津方面に出掛け、昼食は、

沼津魚市場で情報交換をし合う同業の『きえい』さんで食べることにしました。
昼食後に向かったのは、

市内の中心部の商店街にある『正秀刃物店』で、『きえい』さんも『正秀刃物店』の両方の御主人共、知っているのですが、『きえい』さんの方だけ、さん付けなのは、普段からそのように呼んでおり、『きえい』と書くのが憚られるからです。
店内に入り、

受け取ったのは、先々週預け、表面を直してもらった砥石で、以前は、自分でやっていたのですが、一人仕事ゆえ、どうしても後回しになってしまう仕事の一つで、今年になってからは、直してもらうことにしています。
ちなみに、先々週の昼御飯も『きえい』さんで食べたのですが、

その時、玄関前の水槽は、沼津市戸田(へだ)産の高足蟹(タカアシガニ)の住まいでした。
砥石を受取り、

仕上げの方だけ、水に浸け、中砥(ちゅうと)の方は、

以前直した荒砥(あらと)共に、仕舞っておき、ちょっとしたお出掛けも出来、砥石も直ってきたので、リフレッシュして、明日からの仕事に臨みます。
☆★☆ 通販サイト『そのまんま通販』 ★☆★
当店のお取り寄せや通販の商品は、直接の御注文だけでなく、
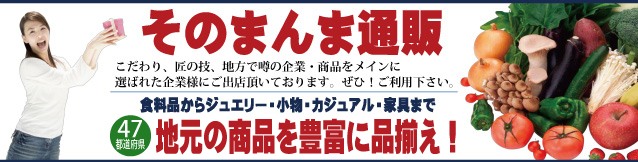
【そのまんま通販】の当店のページからのご注文も可能です。是非、ご利用下さい。
ふぐのイラストが描かれたポーセラーツの器で、昼御飯
午前中上がりのお弁当のご注文を頂くと、否が応でも、仕事を始める時間は早くなるのですが、今日は、9時にお客様が引き取りに見えるので、

5時過ぎから、仕事を始めました。
お弁当のご注文を頂いた時は、普段の段取りをしながら、

お弁当用の料理を仕上げていき、

殆どの場合、最初に仕上げるのが煮物で、煮上げる際、離れていても状況が分かるからだけでなく、その時の食材にもよりますが、煮上げた時、盛り付ける手前が一度で済むからです。
離れていても状況が分かるので、

その間に、玉子焼の準備をしたり、

焼物を仕上げたりし、今日の焼物は、銀鱈の西京焼でした。
仕上った料理を盛り付けるのは、

いつものように、女将兼愛妻(!?)の真由美さんで、

仕上ったら、

上下二段に重ね、仏事用の紐をし、お手元とおしぼりを乗せたら、

風呂敷に包み、

箱詰し、お客様が取りに見えるのを待つばかりとなりました。
ところで、お弁当のご注文を頂くと、余りを昼御飯のおかずにすることが多く、

今日は、先日ポーセラーツの講師をされている常連さんが作ってくれた賄い用の器に、料理を盛り付けることにし、ポーセラーツとは、白い磁器に転写紙などを使い、オリジナル食器が作れるハンドクラフトアートのことです。
御覧のように、

“ふぐに魅せられし料理人”にして、「ふぐに萌え燃え・・・
こちらの大きな器には、

銀鱈の切り落としの西京焼を盛り付け、

煮物と鶏肉の照焼は、

先程の器に盛り付け、お椀以外は、

全てポーセラーツの器にして、賄い@ポーセラーツが仕上り、お昼の美味しいひとときを過ごし、食べ終えたら、

昨日包装したギフト用の『西京漬』を発送しました。
常連さんが、自分と真由美さんに誂えてくれただけでなく、「二人で仲良し子吉で、お昼に萌え燃え・・・
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せ商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
















