会席仕立てのランチの天ぷら定食
当店のランチメニューは、

通年、

こちらの2つのコースを御用意していますが、

これからの時季、当店のオリジナルメニューのサラダ素麺をメインとした“涼し夏(すずしげ)”も、

お召し上がり頂けます。
いわゆる定番としてのメニューはこれらですが、これまで色々な形でお話ししているように、予めご要望をお申し付け下されば、可能な限り対応させて頂いており、そんな変わり種のランチメニューを御用意し、タイトルにもあるように、『席仕立ての天ぷら定食で、その献立が今回のお話しで
日本料理店ですので、会席料理のような仕立て方、つまり出来たてを召し上がって頂きたいので、コース仕立てにし、順番に料理を出しました。
最初に、

先付のうすい豆腐(グリンピースで作った豆腐)をお出ししたら、天ぷらを揚げ始め、

頃合いを見て、天つゆをお出しし、天つゆは一番出汁5に対し、薄口醤油、濃口醤油、味醂(みりん)、赤酒、日本酒が各0,5です。
天種は、

海老、

鯵(あじ)、

南瓜、

ピーマン、

南瓜、

玉葱、

大葉、こしあぶらの8種類で、大葉とこしあぶらのバットは、

氷を入れたバットの上に乗せてあり、へなへなしてしないようにするためなのは、言うまでもありません。
揚がったら、

盛り付け、御飯、

お新香の浅漬、

味噌汁(なめこ、庄内麩、三つ葉)と共にお出ししました。
御覧のように、御飯は昆布御飯で、白御飯でないのは、お客様のご要望によるもので、昆布御飯はかなり薄めの味にしてあるので、天ぷらの味を損ねることはありません。
最後に、

デザートのシャインマスカットと、

ホットコーヒーをお出しし、食後の飲物は紅茶にも変更が可能で、これからの時季は、アイスコーヒーやアイスティーを御用意する時もございます。
先程お話ししたように、会席仕立ての天ぷら定食は、事前予約の特別メニューとなっているだけでなく、天種などもご要望に応じて、色々の御用意が可能です。
なお、詳細については、直接お問い合わせ下さい。
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せ商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
ご家族で、カウンターで天ぷら
今回のお話しは、昨日のお話しの続編というか、本編です。
お子様用の天ぷらと白御飯のセットをお出ししたら、

大人のお客様の天ぷらのコースの始まりで、天種は、

こちらで、順を追ってお話しします。
先付の南京豆腐(南瓜の豆腐)をお出ししたら、

天紙(てんし)と大根卸しを乗せた器と、

粗塩、

天つゆをお出ししたら、

天ぷらを揚げ始めました。
先程のバットにもあるように、海老以外は全て野菜で、

最初はたらの芽で、3月も終わりとなり、今日のたらの芽は天然もので、天然は風味というか香りが、何とも言えません。
お出しする順番に決まりはないのですが、仕事をしやすくするため、火の通りが早いものと遅いものを交互にすることで、お出しすることにしており、たらの芽が揚がる直前に、揚げ始めたのが、

新玉葱で、大きいので、半分に包丁してお出しし、その次が、

スナップえんどうで、春の食材の一つで、スナップえんどうの食べ方で、個人的には一番好きなのが、天ぷらです。
さつま芋は、

スナップえんどうと同時に揚げ始め、

パプリカ、

こごみと続き、こごみは、たらの芽と異なり、栽培ものです。
コースも終わりに近づきつつあり、こごみの次が、

蓮根で、個人的には、もっとも好きな野菜の天種で、

アスパラガス、

南瓜、

海老、

ズッキーニ、

茄子、

エリンギで、この時点で、お客様のお腹の具合を訊き、食事をご用意することにしました。
食事は、

もずく、椎茸、人参のかき揚げを、

天茶に仕立て、天茶とは、天ぷらのお茶漬で、出汁は一番出汁に、塩、日本酒、薄口醤油で味を調えたもので、一つしかないのは、お一方には、かき揚げとしてお出ししたからです。
最後に、

デザートのマスクメロンのアイスをお出しし、お子様には、ミントの葉をあしらってはいません。
デザートをお召し上がりになり、程なくしたら、お帰りになられたのですが、タイミングよく、

次の御予約のお客様が御来店され、個室で会席料理をお出し始めました。
カウンターでの天ぷらのコースは、他のお客様をお断りして、 マンツーマンでのご用意ですので、 天ぷらの御予約を頂いている場合、こちらを優先するので、御来店時間をずらして頂くか、お断りせざるを得ず、一人仕事ゆえ、ご理解頂けると、幸いです。
また、カウンターでの天ぷらのコースは完全予約にして、内容、ご予算など、全てお客様次第ですので、詳細については、直接お問い合わせ下さい。
☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★
毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。
次回は、4月1日(木)の予定です。


放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。
カウンターで、お子様用の天ぷら定食
今夜は、

カウンターで天ぷらのコースを御予約を頂いており、

お子様連れのご家族でした。
大人のお客様は、その都度、揚げてお出しするコース仕立てですが、お子様には、

大人のコースの前に、天ぷら定食というより、天ぷらと御飯をお出し、天種は、

海老、さつま芋、南瓜、ズッキーニ、茄子、アスパラガス、新玉葱、パプリカの8種類で、御飯こそ、小さい茶碗でしたが、食べ応え十分だったようです。
ちなみに、お子様ではありませんが、二人の娘達の夕飯も、

自ずと天ぷらとなり、

天種は野菜のみで、

新玉葱、ズッキーニ、茄子、椎茸、エリンギ、蓮根、アスパラガス、南瓜、さつま芋、パプリカでした。
実は、天ぷらのコースの御予約を頂くと、密かに喜んでいるらしく、先日の夕飯の天ぷらが、

こちらです。
お子様だからと言って、お子様ランチのようなものではなく、今日の様に、大人と同じようなお食事をして下さると、お子様にとっても、良い経験であるのは、言うまでもありません。
世の中には、色んなタイプの飲食店があり、それぞれの違いと良さを知ってもらい、成長して下さって欲しいものです。なお、大人のお客様の天ぷらのコースについては、明日お話しさせて頂きます。
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せ商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
カウンターで天ぷら
これまでにも、何度もお話ししているように、お客様のご要望に応じて、可能な限り対応させて頂いているのですが、先日ご用意したコース料理は、カウンターでの天ぷらのコースでした。
ということで、今回のお話しは、「カウンターで天ぷら」についてで、これに類するものは、何度かあるのですが、今回は御予約を頂いた上でのコースでしたので、初めての試みです。
カウンターには、

飲物のメニューと半月盆をセットしておき、御来店されたら、おしぼりをお出しし、お飲み物を伺い、コース料理が始まりました。
先付の南京豆腐(南瓜の豆腐)をお出ししたら、

天ぷらのコースの始まりで、器に天紙(てんし)を乗せ、卸し生姜を乗せた大根卸しを盛り付け、

お客様の元へ。
それと共に、

天つゆ、

粗塩ををお出ししました。
また、この時の天種は、

これらで、お出ししながら、順次お話ししていきます。
先ずは、春らしく、

たらの芽で、この日は、お客様のご希望で、

蒸し物の鰯つみれ錦糸蒸しをお出ししました。
ここからは、天ぷらのみで、

名残とも言うべき牡蠣、

アスパラガスで、たらの芽同様、春の野菜の一つでもあります。
そして、

さばふぐ、

新玉葱、

椎茸と続き、椎茸は大きいので、

半分に包丁してから、お出ししました。
椎茸の後は、

海老、

蓮根、

最後は、春の山菜の一つのこごみでした。
ここまでで、とりあえずコースは終わったのですが、お食事は、その時のお腹の状態でお決めになるとのことで、天ぷらのコースの締めということで、

天茶で、かき揚げには、玉葱、えのき、人参が入っており、器が違うのは、軽めのご希望があったからです。
お食事を終えたら、

デザートのマスクメロンのアイスをお出しし、「カウンターで天ぷら」は終わりました。
「カウンターで天ぷら」は、完全予約で、内容、ご予算は全てお客様のご要望次第であるだけでなく、マンツーマンでのコースですので、ご希望の日でも、他のお客様の御予約を頂いている時は、お断りしたり、予約時間をずらして頂くこともあります。
こうならざるを得ないのは、ご存じのように、親方無しの子分無しゆえの一人仕事で、詳細については、お手数ですが、直接お問い合わせ下さい。
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せ商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
糠漬(ぬかづけ)の木樽
休みであっても、毎日欠かせないのが、

糠床(ぬかどこ)の手入れで、

御覧のように、元々は日本酒用の木の樽です。
漬ける野菜は、その日によって異なりますが、

今日は、大根、胡瓜、人参で、漬け込んだら、

必ず周りを拭き取るようにしています。
美味しい糠漬を作るコツは、ともかく混ぜることで、冬場で一日に1~2回、夏場で同じく2~3回で、夏場はこれ以上でもかまいません。
あとは、仕上った状態を味見して、塩分を調節し、水分つまり糠床の硬さを加減するだけです。
とは言え、注意していても、真夏は、急に味が変わることもあり、そういう時は、糠床を捨てて、新しい糠を加えたりしており、何年やっても、一筋縄ではいかないのが糠床で、それこそ生き物相手ゆえ、気を抜くことは出来ません。
ですので、糠漬の味をお客様に褒められると、他のどんな料理も嬉しく、今お話ししたように、一筋縄ではいかないだけでなく、ここまでの糠床にするのは一朝一夕では出来ないからです。
ところで、手入れの度に、きれいにしていても、周りについた糠が乾いてしまい、それが糠床に落ちると、味だけでなく、糠床の劣化に繋がるので、

木樽を洗うことにし、

糠床を鍋に移したら、

木樽をシンクに入れ、

水を注ぎ、そのまま放置しておき、落ちやすくなったら、

たわしで洗い、

蓋と共に乾かしておきました。
乾いたら、

鍋から、

糠床を移し、

きれいになった木樽で、

糠漬を漬け始めました。
ところで、糠漬に興味がある方に、何度も差し上げたことがあり、今後も、そのような方がいらっしゃれば、喜んで差し上げたいと思っておりますので、糠漬にチャレンジしたい方がいらっしゃれば、お気軽に声を掛けて下さい。
★☆★ 通販サイト『そのまんま通販』 ☆★☆
当店のお取り寄せの商品は、お電話、SNSなどの直接のご注文だけでなく、
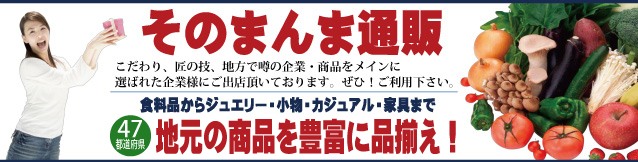
【そのまんま通販】の当店のページからのご注文も可能です。ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
二皿に分けた天ぷらの盛り合わせ
コース料理の献立には、基本的に、何らかの揚物をお出ししているのですが、御予約の際にお申し付け下されば、色々と対応とさせて頂いております。
そんな今日は、

天ぷらの盛り合わせを御用意したのですが、多めの御注文でしたので、

二皿に分けて、

天つゆと共に、お出ししました。
最初にお出しした天種は、

海老、椎茸、蓮根、ズッキーニで、後のそれは、

鯵、エリンギ、玉葱、赤ピーマン、大葉でした。
こういう時に注意するのは、2種類の魚介類が別々になることや、同じ形に包丁した天種を別々にすることで、この場合、玉葱と蓮根が同じ形になり、盛り付けた時のことを考慮しているだけでなく、赤系の目立つ色も別々になるようにもし、こちらの方が、盛り付けの際には重要です。
また、御注文ゆえの料理ゆえ、天種も、お客様のお好みに応じての御用意で、冒頭だけでなく、これまでにもお話ししているように、予めお申し付け下されば、可能な限り、対応させて頂きますので、宜しくお願い致します。
『佳肴 季凛』のFacebook(フェイスブック)ページ
Facebook(フェイスブック)にはじまり、



それぞれにアカウントがあり、それぞれで投稿しているのですが、『佳肴 季凛』=志村弘信ということもあり、ユーザーネームやアドレスなどの類も同様です。
とは言え、Facebookだけは、『佳肴 季凛』のページがあり、

簡素なホームページなトップページのような感じで、色々と投稿しておりますので、どれもこれも、お時間が許しましたら、御覧下さい。
★☆★ 通販サイト『そのまんま通販』 ☆★☆
当店のお取り寄せの商品は、お電話、SNSなどの直接のご注文だけでなく、
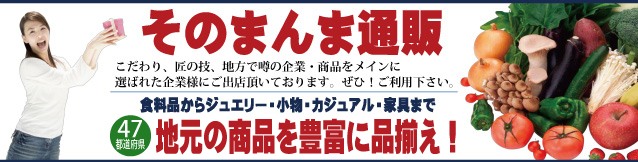
【そのまんま通販】の当店のページからのご注文も可能です。ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
総仕込みの準備
明後日(6日)から、新年の営業をすることもあり、明日は仕込みをするのですが、それこそ総仕込みとなります。
そんなこともあり、今日は、仕込みの準備をしたのですが、

仕込みという言葉そのものが、準備を意味しているので、仕込みの準備とは、不思議な言い方としか思えません。
バットやボウルを洗ったら、

拭き上げ、乾かしておきました。
その後、冷凍庫の在庫も殆どない【西京漬】を仕込まなくてはならないので、

西京味噌を仕込み、

真空パック用の袋などを用意し、 一番出汁を引くため、

鍋に昆布と干し椎茸の足を入れ、仕込みの準備が終わりました。
ところで、ホームグランドとも言うべき沼津魚市場は、

今日まで休みで、明日が初市で、先程お話ししたように、【西京漬】用の魚でもある銀鱈(ぎんだら)、サーモン、鯖(さば)をはじめ、仕入れに行って来ます。
☆★☆ 【コエタス】 ★☆★
当店のお取り寄せ商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。
一年の計は、ふぐ にあり
にあり
新年、萌え燃え・・・

おめでとうございます。中略ということで、今年も、どうぞ宜しくお願い致します。
“ふぐに魅せられし料理人”ゆえ、一年の計は、ふぐにありということで、

“ふぐ納め”のひれを干したら、

元旦ということで、

にごり酒のハイボールでおめでとちゃん♬
冷蔵庫にあるものを適当につまみながら、志村家の女三羽烏もいないし、正月となれば、

熱燗にシフトし、あては、海鼠腸(このわた)。
朝酌にして昼酌であるだけでなく、正月ゆえ、

海鼠腸掛けの磯辺餅。つまみにして、食事は、正月ならでは・・・♬
昼酒の素晴らしさは、夜に飲むよりも、少ない量で良きにして酔い心地に浸れることであるだけでなく、平和な気分になれ、自分の中では、間違いなくノーベル平和賞です。
世界中の治政者が昼酒をたしなめば、間違いなく、この世の中から、争いことはなくなるのは間違いなく、そのことに早く気付いて欲しくてなりません。(笑)
平和な気分に浸っているうちに、昼寝と、さらに平和な気分に浸り、陽が落ちる前に目が覚めただけでなく、酔いも冷めたので、夕飯の準備をし、“ふぐに魅せられし料理人”の元旦の晩餐は、もちろん、

ふぐ料理しかなく、その美味しさにうっとりし、再び平和な気分に浸ったのでした。
ところで、暮れの時点で、新年の営業は、3日からの予定だったので、暮れの忙しなさもあり、ホームページの営業日のカレンダーは、そのままとなっておりますが、

6日からです。
本年も、多くの方の御来店、心よりお待ちすると共に、改めて、宜しくお願い致します。
すし酢の作り方
今日は、

お持ち帰り(テイクアウト)の〆鯵重(しめあじじゅう)をご用意し、その仕立て方については、こちらをお読み下さい。
また、今日の〆鯵は、

昨日、

沼津魚市場で仕入れた鹿児島産のもので、

仕込んだのですが、

〆鯵の仕込みについては、こちらをお読み下さい。
今日は、趣を変えて、白米に黒米を入れたものを炊き、酢飯にしたのですが、すし酢と合わせると、黒米のアントシアニン色素が酢と反応して、薄いピンク色になり、その様子は後ほど・・・。
黒米を入れて炊く場合、芯が残るので、予め黒米だけ水に浸けておき、

白米を研いでから、

合わせてます。
さて、メインである〆鯵も肝心ですが、酢飯の味を決めるすし酢も、同じくらい肝心で、今回のお話しは、すし酢の作り方です。
すし酢と一口に言っても、料理人というより、鮨職人によって様々なのは言うまでもなく、自分の場合、料理の道に転がったのが鮨屋ということもあり、その時の割、つまり分量を基にしています。
使うのは、

酢、赤酒、味醂、薄口醤油、日本酒、てん菜糖、塩で、

てん菜糖と塩を鍋に入れたら、

他の調味料を合わせ、

火に掛け、

ひと煮立ちしたら、火を止め、出来上がりです。
冷めたら、別の容器に移し、冷蔵庫にしまっておくのですが、水を使っているだけでなく、酢が殆どなので、常温で保存することも可能です。
酢飯にする時は、炊き上がってから5分ほど蒸らしたら、

バットに移し、

すし酢を掛け、合わせると、

先程お話したように、酢とアントニアン色素が反応して、淡いピンク色になり、黒米の量が多いと、さらに色がつき、御飯1合に対し20ccの10:1が、その割合になります。
ちなみに、今日のご注文が夕方だったこともあり、

真梶木(まかじき)と〆鯵のハーフ&ハーフ丼にし、自分好みの魚と酢飯ゆえ、納得の味だったのですが、自分の好みのすし酢は、塩とてん菜糖が同割のものです。
塩分が多いのは、元々の江戸前鮨の仕事で、江戸前鮨は立ち食いと言われるように、その場で食べるもので、立ちとは、鮨屋の符牒で、カウンターを意味し、その語源は、屋台でお客様が立って食べることに由来し、職人が握っていたのが、元々のスタイルなのです。
一方、糖分が多いと、冷めても米が硬くならないので、出前メインの鮨屋では、そういう割にする傾向があり、その例がスーパーの鮨で、所謂(いわゆる)惣菜ゆえ、リーズナブルな値段にするため、使える魚の原価にも限度があるので、その味を補うため、糖分で甘味と旨味を感じやすくしています。
さらに言うと、スーパーの場合、冷蔵ケースに陳列するので、糖分を多めにしないと、酢飯が硬くなり、食感が劣るのが避けられないのも、その理由でもあります。
日本料理が自らの道ですが、鮨屋卒というか中退の身ゆえ、〆鯵のような光物や、貝類の小物の仕込みを憶えることが出来、中でも貝類の仕込みは、様々です。
鮨屋で憶えた仕事は、今となっては貴重な財産であるだけでなく、様々な想い入れがあり、仕事は身体で憶えてこそで、一人仕事の身ゆえ、教えてくれる先輩や親方はいなくいても、自ら憶える姿勢を失うことなく、厨房に立ち続けます。
☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★
毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。
新年は、1月7日(木)の予定です。


放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。
2020.12.25|お持ち帰り(テイクアウト) 季凛 魚 |permalink|コメントはまだありません















